マンションをリフォームし、床については無垢のパイン材とコルクタイルを使用しました。
すべての床を無垢材とすることも考えたのですが、脱衣所だけは水に濡れやすい環境であることを考慮してコルクを採用しました。
ここでは、リフォームして約1年経過したそれぞれの床材の状況を紹介したいと思います。
床材の選定
リフォームを行うにあたり、床材については自然素材を使用したいと考えていました。
そのため、当初から無垢の床材を使用することを考えていたのですが、価格的には決して安いものではないため、その中でも比較的コストを抑えることができるものを選ぶようにしました。
そして最終的に、柔らかくて温かみがあるパイン材を採用することにしました。
また、脱衣所についても、自然の質感を持ちながら水に強い材料を探し、最終的にコルクを選定しました。
コルクは、『水を吸いにくく蒸発も早い』、『触感が温かく断熱性が高い』、『無垢の床材と同様に自然な質感・素材感がある』などの特徴を持つことから、今回のリフォームで採用するには最適と考えました。
リフォーム直後の状況
パイン材とコルクのリフォーム直後の状況は以下のとおりです。
パイン材
リフォーム直後は、色合いが薄くて明るく、いかにも床を張り替えましたという印象でした。
それはそれで良いのですが、経年により色が濃くなり、落ち着いた雰囲気になることを前提として考えていました。

リフォーム直後のパイン材
コルク
コルクは当初から落ち着いた色合いでした。
色は、実際の見本を見て決めたのですが、もう少しパイン材との整合性を考えた方が良かったと反省しています。

リフォーム直後のコルクタイル
約1年が経過した無垢のパイン材の状況
約1年が経過したパイン材の状況が下の写真です。
マットを敷いていた部分と、そうでないでない部分との違いがはっきりと表れるようになりました。

約1年経過後のパイン材
時間とともに色合いが濃くなっており、落ち着いた雰囲気になりつつあります。
個人的には、もっと深い色の方が好きなので、今後さらに変化していって欲しいと思っています。
パイン材の質感や歩行感は、非常に心地良く思っています。
合板などと比べて、夏場のベタ付きや冬場のヒンヤリ感はありません。
ただ、冬の乾燥した時期には材料が収縮し、目地(板どうしの隙間)が開く傾向にあります。
気になるほどではありませんが、細かいゴミなどは目地に入ってしまうこともあり得ます。
しかし、目地幅が変化するのは、無垢材のメリットである調湿効果が機能しているからであるとも言えます。
無垢材は、室内の湿度が高くなるとその水分を吸収し、逆に湿度が低くなると水分を放出するという特徴を持つためです。
基本的に、目地のゴミは掃除機でキレイになりますので、目地にゴミが入るといったデメリットよりも、調湿効果というメリットの方がはるかに大きいのではないかと思います。
約1年が経過したコルクタイルの状況
約1年が経過したコルクの状況が下の写真です。
写真に示した位置にマットを敷いているのですが、それ以外の部分と何も違いはありません。

約1年経過後のコルクタイル
基本的に、この1年で色合いの変化はなかったと言って良いと思います。
なお、コルクは日差しが当たると色があせてしまうので、床には直接日差しが当たらないようにしています。
材料の質感や歩行感は、無垢材の方が自分の好みではありますが、コルクも決して悪くはありません。
柔らかさがあり、冬場でも冷たさを感じないので、脱衣所には適していると思います。
そして何より、耐水性が高いことが魅力です。
浴室を利用した後、どうしても床面が濡れてしまうことがありますが、その跡が残るようなことはありません。
もちろん、大量の水で濡れたまま長時間放置しておくと、その部分が劣化してしまいますが、普通に利用している範囲では、何の問題もありません。
やはり、脱衣所については、コルクタイルを選択して良かったと感じています。
リフォーム後1年が経過して思うこと
床をリフォームして約1年が経過しましたが、無垢のパイン材、コルクタイルとも、採用して正解だったと思っています。
特に、コルクについては、水に強いこと、ヒンヤリ感がないことなど、思っていた以上に優れた材料だと感じています。
今回は、脱衣所だけにコルクを使用しましたが、次回、リフォームする機会があれば、もう少し利用範囲を広げても良いかなと考えています。
以上、リフォームして約1年経過したパイン材、コルクタイルの床材の状況について紹介しました。
![]()
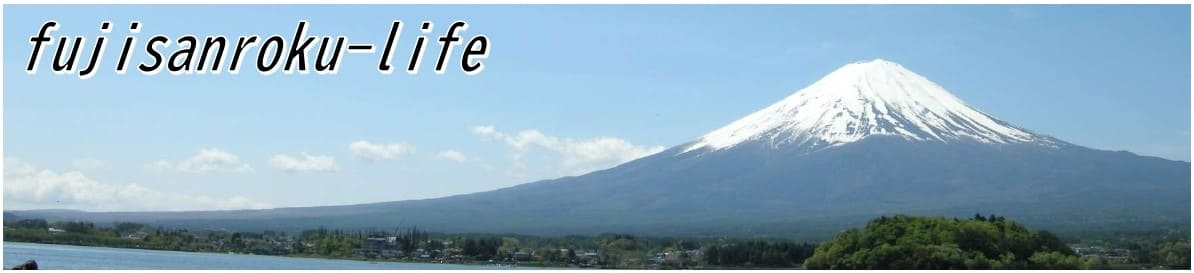


コメント